摂食嚥下評価入院
当院では2023年度より摂食嚥下(せっしょくえんげ)に関する取り組みを強化しています。
「摂食嚥下」とは
「摂食」とは「食べること」を指し、「嚥下」とは「飲み込むこと」であり、食物を口の中から食道を通って胃に送り込むことです。口腔(口の中)や食道に異常があり、嚥下が困難になる状態を摂食嚥下障害といいます。
この度、摂食嚥下支援チーム「N-EAT(エヌイート)」を立ち上げました。
N-EATは「Nishioka-Enge Anshin-Team 西岡-嚥下-安心-チーム」の頭文字で【EAT=食べる】ともかかっています。
チーム名に「安全」ではなく「安心」という言葉を用いたことには理由があります。
誤嚥性肺炎や嚥下機能の低下がある患者さんの「食べたい」という素直な気持ちに、スタッフ一同真摯に向き合っていきたい、「安全」には嚥下が出来ないにしろ、少しでも「安心」して食べて欲しいという気持ちを込めて言葉を選びました。
人生の最終段階で好きなものを食べたい、飲みたいと思っている患者さんやご家族の想いに寄り添い、誤嚥のリスクを抱えながらも最期まで食べる、飲むことを諦めない支えが出来ればと考えています。
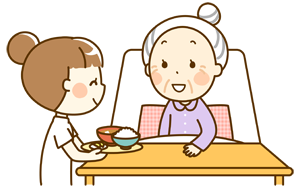
当院では「摂食嚥下評価入院」の導入を始めました。言語聴覚士を5名配置し、毎週火曜日に北海道大学病院リハビリテーション科 梅森 秀医師にお越しいただき、嚥下内視鏡検査やリハビリテーションの評価を行っています。摂食嚥下評価入院のご相談は、当院医療介護相談センター医療ソーシャルワーカー(代表:011-853-8322)までご連絡ください。
N-EATの特徴
① リハビリテーション医の診察・評価
専門医による摂食嚥下機能評価を受けられます
② 介護者の休息を目的とした入院期間に摂食嚥下機能評価を実施
摂食嚥下機能評価期間は7日〜10日間ほどです
③ 評価結果に基づくリハビリテーションの継続
評価後も必要に応じて、摂食嚥下リハビリテーションを継続できます
④ 処方の適正化
患者さんの嚥下機能に合わせた最適な薬剤形態を選択できます
⑤ ベッドサイドでの検査が可能
移動に伴う負担が少なく、患者さんの状態に合わせた検査を実施できます
摂食嚥下評価入院(目的)
- 嚥下障害の様子と障害の部位(口腔・咽頭・食道)を明らかにします。
- 摂取した食物が誤嚥(食物が誤って気道に入ること)しているかどうがを明らかにします。
- 食物の形状や体位、摂取方法などを調整することで、安心して食べることができる方法を探します。

▲ N-EATの活動の様子
嚥下評価入院の流れ
入院1日目
基本検査
食事状況確認
採血
レントゲン
食事場面観察
基本検査
食事状況確認
採血
レントゲン
食事場面観察
入院2~6日目
嚥下検査・評価
嚥下造影検査
嚥下内視鏡検査
嚥下検査・評価
嚥下造影検査
嚥下内視鏡検査
検査終了翌日~
結果説明
食事形態の提案
退院調整
結果説明
食事形態の提案
退院調整
摂食嚥下機能評価入院に関するポスター
摂食嚥下機能評価入院に関するポスターを作成いたしました。
当院で行っている「摂食嚥下機能評価入院」の特徴や入院期間などが記載されています。
ご相談、お問い合わせは医療介護相談センター 医療ソーシャルワーカーまでご連絡ください。
「嚥下調整食試食会」を開催いたしました
令和7年9月9日(火)、札幌医科大学附属病院 摂食・嚥下障害看護認定看護師 船水 良太氏を講師にお招きし「嚥下調整食試食会」を開催いたしました。
詳しくはこちらから


